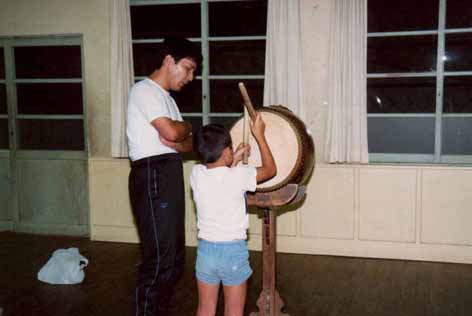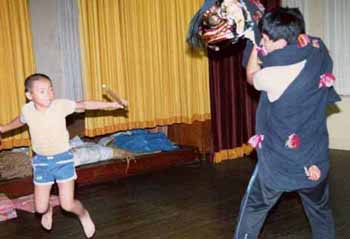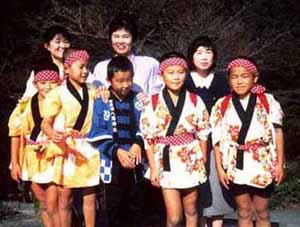| 荒川八幡神社地方祭あれこれ |
☆燃える神輿☆

火をつけて燃やされる神輿(昭和58年)
昭和58年、八幡神社の550周年を記念して社殿を新築した際に
神輿も新造しました。
役目を終えた旧神輿は、氏子の見守る中、八幡神社において燃やされる
運命になりました。
炎に包まれた神輿は、何か寂しさを感じます。
|
☆秋祭りに向けて☆
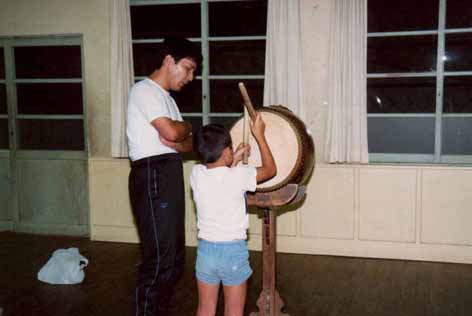 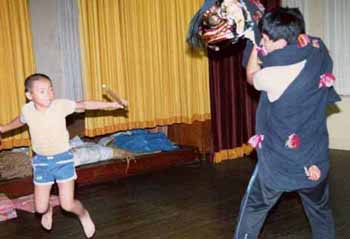  
「なぶりこ」の練習風景(平成元年) 獅子頭と「なぶりこ」の練習(平成11年)
荒川の獅子舞は、リズムが早く激しい舞が特徴です。
太鼓のたたき方も複雑で、マスターするのは並大抵ではありません。
楽譜もなく、口づたえで教えることになります。
時には厳しく、時にはやさしく、繰り返し、繰り返し練習が続きます。
写真は、旧加茂地区公民館での練習風景です。
|
☆文句あるか☆

観客に向かっておそいかかる獅子(昭和60年)
お祭りの当日、若者は酒を飲み、神輿を担ぎ、獅子を舞いと
大忙しです。
特に酒を飲んだあとで舞う獅子はつらいものがあります。
写真は、舞っている途中でやじが飛び、かっとなった
獅子が観客に向かって襲いかかっていところです。
お祭りならではの一こまです。
無視された「なぶりこ」のけげんそうな顔が印象的です。
|
☆「なぶりこ」4人☆
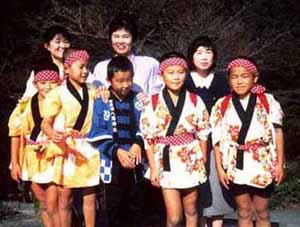 
4人の「なぶりこ」の記念撮影(平成2年) ふたたび「なぶりこ」4人(平成13年)
獅子舞の「なぶりこ」は、昔から2人と決まっていました。
しかし、過疎化により
平成2年には、小学生の男の子が4人になってしまいました。
後継者の育成が急務と言うことで、平成2年には4人の小学生に
獅子舞の太鼓を教えました。
そういうわけで、平成2年から平成7年までの6年間、「なぶりこ」
が4人になりました。
これは、長い秋祭りの歴史のなかでもはじめてのことでした。
その後、平成11年に初めて女の子の「なぶりこ」が誕生し、平成12年からふたたび4人の「なぶりこ」が登場することになりました。
|
☆暴れ獅子☆
 
暴れる獅子と「なぶりこ」(平成3年)
お祭り当日の「なぶりこ」は大変です。
太鼓をしっかりたたかないとやじが飛び、写真のように
暴れ狂う獅子をかわしながら太鼓を叩かなくてはなりません。
「なぶりこ」は祭りの主役であり、それだけ重要な役割を持っています。
|

荒川の獅子舞へ戻る |